
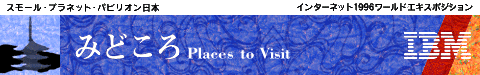

世帯数10,000余の市内に、なんと2,600 棟余りの蔵があります。数の多さだけでなく、倉庫、醸造蔵、座敷蔵、店蔵などと、その用途も 多種多様。さらに、まちの中心街には、銀行、学校、郵便局、美術館など、蔵造りの近代建築物があり、まさにまち全体が蔵の博物館に なっています。わがまちのナンバー1は、蔵の数とその用途の多様さにあります。
 |
店蔵土蔵造りの店蔵は、明治初期のころから建造されはじめました。道路から店に入ったところに、幅一間の土間が設けられ、土間と店は 蔀(しとみ)と呼ばれる板戸で仕切られています。板戸の外側には、三尺幅の縦長の土戸をかけて防火と盗難防止をはかり、周囲はす べて土壁で覆われています。 |
貯蔵用の蔵貯蔵用の蔵は、町家、農家の別なく、たくさん建てられています。土壁や砂壁のままのものや、観音開きの窓の部分だけが白漆喰 (しっくい)のものなどがみられます。町家は商品や質草の保管、農家はみそ、しょうゆ、塩、五穀類や、衣類を入れたタンス、冠婚 葬祭の調度品などを保管しています。 |
 |
 |
醸造蔵醸造蔵は幕末から明治にかけて造られ、天秤梁(てんびんはり)などの和式小屋組み、洋式の真束小屋組みが多い。表面を覆う壁は土砂壁 漆喰壁で、内部は三尺おきに柱を露出させています。醸造蔵の主流は酒造蔵で、次いでみそ、しょうゆ、麺(めん)蔵、ほかに漆喰塗りの 漆器製などもあります。 |
レンガ蔵レンガ蔵は、明治に入ってレンガ工場とともに生まれ、蔵座敷、貯蔵蔵、作業蔵などに使われています。骨組み全体をレンガで囲む レンガ蔵は、腰から屋根にかけてレンガを積み重ね、屋根は壁土とレンガを敷き並べた上に瓦をふくという工法で、ジャバラはありません。 アーチ式の玄関と窓は、鉄格子に板戸、あるいは土戸で閉じています。 |
 |
 |
蔵座敷の技法が完成をみたのは、明治末から大正期で、用材も欅(けやき)、縞柿、黒檀、鉄刀木と幅広いものがあります。一室すべて を縞柿や欅材で造らせた座敷、伝統的な床や脇床の工法、天袋、地袋に描かせた南画や四条派系の絵画など、資金と時間に糸目をつけず、 美の極致を追求しています。 |
 |
外壁蔵の美しさの一つに外壁が挙げられます。外壁には土、砂壁、白、黒漆喰などが使用されます。土壁に使用される土は、粘着力があり水 を吸収しにくいものが選ばれます。一般に、ツタやワラを混ぜた荒壁の上に砂壁を塗り、仕上げは白漆喰か、白漆喰の上に黒漆喰を塗り ます。耳塗り袋塗りの二通りがあります。
観音開きの扉観音開きの扉は、下前を女戸、上前を男戸と呼びます。扉の外面は外子、内面は内子といわれ、内子の中央に開閉の金具がつけられます。 窓における観音開きの扉の場合、表面から小面(こづら)の部分、あるいは、かけごと呼ばれる側面の部分の美しさには、特に技術を 要するといわれています。 |
 |
屋根の形には、削屋根(二重屋根)とジャバラ(蛇腹)をつけたものとの二つがあります。
削屋根削屋根は、屋根の部分を土で固め、土垂木(たるき)をつけ、その上を荒壁、砂壁の順に5寸ほどの厚さで塗り、屋根を支える猫石を 置きます。削屋根は普通、合掌に組まれ、積雪の重さや風などの外圧が加われば加わるほど、堅く締められる工法になっています。 |
 |
ジャバラのついた屋根ジャバラのついた屋根は、瓦などでふかれる屋根の部分を除いて、すべて壁で塗りつぶす方法です。 いずれも切妻屋根の小屋組みで、棟木、軒桁に渡される垂木の先端にジャバラがつけられます。ジャバラの部分は、一枚の板や木割に カーブをつけ、曲線を描かせる方法で、くりジャバラと垂直の切り立てジャバラがあります。 |