

漆器
会津漆器の起源は、8世紀後半(平安時代)で、地場産業としての基礎が整ったのは16世紀の後半です。以来400年余り、この会津漆の伝統を 受け継いで、飯豊山から産出される良質木材と盆地特有の気候条件のもとで上質の漆器の産地として栄えてきました。喜多方の漆器の特徴は、日常使われる椀や盆などが数多く生産されることです。また漆器づくりには、ほこりと湿気が禁物で、それらの 影響の受けにくい「蔵」が作業場としてたいへん重宝されました。今でも、漆器職人の住んでいる菅原町には「蔵」が多く残っています。

  |
漆器会津漆器の起源は、8世紀後半(平安時代)で、地場産業としての基礎が整ったのは16世紀の後半です。以来400年余り、この会津漆の伝統を 受け継いで、飯豊山から産出される良質木材と盆地特有の気候条件のもとで上質の漆器の産地として栄えてきました。喜多方の漆器の特徴は、日常使われる椀や盆などが数多く生産されることです。また漆器づくりには、ほこりと湿気が禁物で、それらの 影響の受けにくい「蔵」が作業場としてたいへん重宝されました。今でも、漆器職人の住んでいる菅原町には「蔵」が多く残っています。 |
桐会津桐の質の高さは有名で、その桐から作られる桐下駄も、軽さと履き心地の良さには定評があります。ここ喜多方でも桐下駄の工場が 何軒かあり、庭には「輪積み」と呼ばれ、乾燥させるため桐下駄を塔のように高く積み重ねた独特の光景がよく見られます。また桐のエ ピソードには、「会津地方では昔から女の子の誕生を祝って桐の苗木を植え、その子が成人して嫁ぐ時に、その木を切って桐タンスを作 り、嫁入り道具として持たせてやる」という習慣がありました。なかなか美しい話ですね。この桐のタンスは、火に強くたいへん燃えに くいことでも有名です。 |
 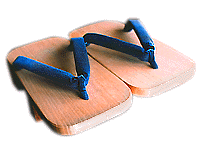 |