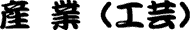絣が織られるようになったのは,江戸時代になってからで,木綿の普及によって,初めて民衆の間で
染織が行われるようになりました。
そこから絣が生まれ,木綿と絣の結びつきが生まれました。絣は昔から多くの人々に親しまれてきた織物
です。芦品郡新市町一帯は備後絣の本場です。
嘉永6年(1853),富田久三郎が中田屋万兵衛の「キシ縞」という浅黄絣の絹織物の技法を参考にして,
手引糸を使って縦糸の一部を竹の皮でくくり,それを染めて井桁絣を考案したのが備後絣の初めです。
この備後絣は模様が素朴で独特の美しさが特徴です。
|
 |