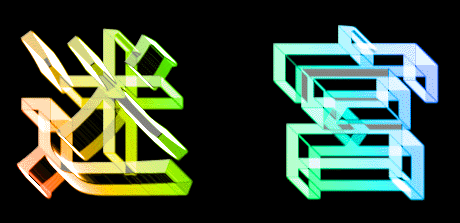 能の迷宮
能の迷宮
 Japanese Home
Japanese Home
しかし、師匠の家は終戦の年までは、その年に廃絶した「春藤流」という流派の家元預かりの家だったのです。
能の流派は江戸時代に幕府によって定められて以来、その数を増やすことはありません。あとはその流派が存続していくか、「廃絶」という消滅をしていくかだけです。
「春藤流」は、昭和20年、終戦の年までは存続していた流派です。しかし、その年、家元預かりだった方の死によって途絶えてしまって現在に至っています。
謡本や型付けなどの「春藤流」に関する資料の多くは戦火に焼けて烏有に帰してしまいました。しかし、一時はかなり隆盛だった流派ですし、流儀が廃絶してたった50年しかたっていません。今でも日本のどこかにそれらの資料が残っているはずです。
そして、そのような資料の存在する噂だけはよく耳にします。
しかし、残念ながらそれらが出てくることはほとんどないのです。
今、インターネットという、個人でも楽に使える相互情報ツールを私たちは手にすることができました。インターネットを通じて、それらの資料を発掘できればと思っております。
ただ、50年前の「春藤流」の存在はご存じの方の多くはインターネットにアクセスをしていないと思います。そこで、みなさんやお知り合いの中で「春藤流」の謡を伝えている方、あるいは蔵の中に眠っている資料などがありましたら、ぜひご連絡をいただきたいと思っております。
このホームページの正式な公開は4月になる予定ですので、それ以降資料が集まった状況の推移を、定期的に書いていきます。
<続く>