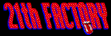ローリング・ストーンズ、その所以 Pt.2
ローリング・ストーンズとは、紛れもなく音楽史上最高位のロックンロール伝道師である。
しかし、そのイメージだけが先行し、ロックンロールの一点だけで語られることの如何に多いことか。
実際ストーンズ・ファンの大半は、そのイメージと合致したハード・ビートだけに酔いしれ、
ファンであることに満足し、ストーンズを理解したつもりでいるのではないか。
ガンズやエアロスミスを傘下に置きつつ、ピストルズやドールズと同様の感銘を覚えるのもストーンズの強みではあるものの、
それだけで語られるのは悲劇以外の何物でもないのである。
|
|
ロックンロールが、R&B〜ブルースへの憧憬のもとに発生したことは言うまでもない。
故にロックンロール・バンドとして最高峰のストーンズがR&B〜ブルースに長けていることは当然の事実である。
しかしストーンズの偉大さはR&B〜ブルースの良き理解者であることだけに留まらなかったところにある。
言い換えれば、R&B〜ブルースへの理解は、ストーンズの音楽的探求心の第一歩にすぎなかったということである。
ブルースやR&Bと土壌を同じくするところ、すなわち民衆〜大衆的レヴェルから生じた音楽性を貪欲に消化し、
またそれら音楽性をロック・ファンにいち早く紹介してきたのである。実際、今ではレゲエも市民権を得ているものの、
いまだその発音もままならずレガエとかレガなど呼び方も定かではなかった頃、
ストーンズがそれを取り上げる毎に、ポピュラー・シーンに浸透していったのである。
そのレゲエやダブといったジャマイカはもとよりアフリカまで見据えた黒人音楽への洞察力の凄さよ。
これがなければ"シンパシー・フォー・ザ・デヴィル"や"ラクシャリー"といった傑作は生まれなかったであろうし、
その感性の集大成が"コンティネンタル・ドリフト"であると言いたい。
|
|
ストーンズがR&B〜ブルースのみならず広義の黒人音楽への憧憬と洞察力のもとにその音楽性を支えられているということは意外と語られることが多いものの、
それだけで結論としてしまっているケースが殆どであり、それではストーンズの魅力の半分も理解したことにはならないのである。
彼等の音楽的探求心は黒人音楽のみならず民衆〜大衆レヴェルに於ける音楽性全般に向けられているからである。
すなわち土に根差す音楽性にアプローチしているということである。故のアメリカン・トラッドとしての白人音楽〜マウンテン・ミュージック
〜カントリー・ミュージックへの傾倒である。そして、それに付随するところのテックス・メックス、レッドネックス等の習得。
そこから"デッド・フラワーズ"や"インディアン・ガール"そして"ファー・アウェイ・アイズ"の傑作が生まれた。
また、その最たる例として"ワイルド・ホーシーズ"を挙げたい。
なんせ、その筋の大家グラム・パーソンズとの相互作用から生まれた名曲なのであるから。
そして、この感性の集約が"ベガーズ・バンケット"として、
いまだカントリー・ロックという言葉も定着していない1968年に発表されていることは驚異である。
また、このトラディッショナルな白人音楽と黒人音楽とが折衷したところにスワンプ・ロックというカテゴリーが生まれてくるのではあるが、
それすら既に"レット・イット・ブリード"として69年に早くも呈示しているのだから信じられない。
しかし、ロックンロールとはそもそもR&Bとカントリー・ミュージックとを合成して生まれたものであるだけに、
ロックンロール・バンドとして最高峰のストーンズが、この手に長けているのもこれまた当然と言うべきなのかもしれないが…。
|
|
これまでを要約すると、大衆文化であるところの伝統的な音楽性に新しい息吹きを与え、
広くロック・ファンに紹介しているということになるのであり、
ならばこれと同傾向のアーティストと言えばザ・バンドやライ・クーダーに他ならないのである。
ところが、ストーンズの場合伝統音楽を歴史的に溯って研究するだけで済ませていないところがま凄いのである。
それだけでは現在見受けられるような、21世紀に向けての推進力といったようなものは生まれようはずがないのである。
つまり、テクノロジーをも踏まえた上でのコンテンポラリーなセンスこそがそうさせているのである。
ストーンズが転がり続けるストリートも時間と共に常に変化するのである。
そしてそこから生まれた現実的なストリート・センスにファンク・ヒップ・ホップ〜ラップ等が存在し、
言うまでもなくストーンズはそれらを容赦なく接種してきたのである。
ハイ・サウンドを意識した"ダンシング・ウィズ・ミスター・D"ブルー・マジックをコーラスに従えた"イフ・ユー・リアリー・ウォント・トゥ・ビー・マイ・フレンド"
過激なミキシングが印象的な"アンダーカヴアー・オブ・ザ・ナイト"等その都度コンテンポラリーなストリート・センスに溢れていたのである。
ミック・ジャガー自身"ミス・ユー"こそ70年代を象徴する作品であると言うその真意もここいらにあると言えるのかもしれない。
ともあれ、R&B〜ブルースを筆頭とした土に根差す音楽性を貪欲に吸収すると同時に、ファンク〜ラップといった最先端のストリート・センスをも吸収してきたのがストーンズなのである。
すなわち大衆音楽を歴史的に掘り下げると同時にコンテンポラリーなセンスをも身につけているのである。
故にいつの時代のストーンズも、デビュー当時のロックンロール・スピリットとキャリア分だけの円熟味が同居しているのである。
そして、そのことを目の当たりにしたのが90年と95年の来日公演であったことは言うに及ばない。
最新テクノロジーまでをも見事にロックンロールさせつつ、若々しくも滋味深く、オーセンティクかつコンテンポラリーなローリング・ストーンズがそこに存在したのである。
とにかく"It`s only Rock&Roll, but I like it"とうそぶくストーンズを真に受けてはならない。
彼等が再現する音楽は決して"ロックンロール"という語感から想定できる程度の許容量ではないのだから…。
※本稿のタイトルにPt.2とありますが、マディー・ウォーターズやチャック・ベリー等を引き合いに出した緒論が適当に存在するため、
それら一般的ストーンズ論を全て、Pt.1とかえさせて頂きこのタイトルと致しました。故に本稿にPt.1は存在致しません。
悪しからず…。