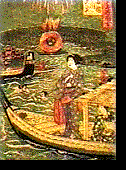
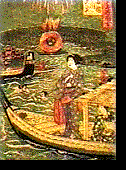
17世紀後半「大名の贅沢は隅田川にとどめをさす」と言われるほど舟遊びは豪華なものでした。始めの頃の納涼花火は、花火を売る舟が多くの屋形船の間を漕ぎ廻り、客の注文により花火を上げるというものでした。『東都歳事記』には両国の川開きについて書かれています。両国の川開き花火のきっかけとなったのが、享保17年(1732)の大飢饉です。全国的な凶作が起こり伝染病コロリ(コレラ)が流行、多くの死者を出しました。享保18年(1733)時の将軍吉宗はその死者の霊を慰め悪病退散のために花火を打ち上げたのです。これが世にいう両国の川開き花火の始まりです。
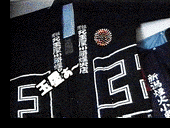
「玉屋ぁ〜鍵屋ぁ〜」今も花火の季節にはこんなかけ声が聞こえてきます。鍵屋、玉屋の二大花火師は両国の川開き花火を支え発展させてきました。この二人無くして日本の花火史は語れません。享保18年(1733)の初めての川開きの花火師が6代目鍵屋弥兵衛。その時打ち上げた花火の数は20発ほどのものでした。それでもその噂は江戸中を駆けめぐり、多くの人を集める年中行事となっていったのです。玉屋は鍵屋の暖簾分けで、花火作りの名人と言われた清七が玉屋市兵衛を名乗ったのは文化7年(1810)のことです。以後、川開きは、上流に玉屋、下流に鍵屋がそれぞれ舟を出し、2大花火師の競演となりました。
玉屋の人気は鍵屋を凌ぐほどのものでした。この頃の浮世絵の画題になっているのは玉屋でした。ところが天保14年(1843)玉屋は失火によリ全焼、町並みを半丁ほども類焼させ、江戸を追放されてしまいました。1代限りで断絶した玉屋と戦前まで続いた唯一の江戸の花火屋鍵屋の競演はわずか、32年でピリオドを打ったのです。

明治維新、文明開化の波に乗り、花火の世界も大きな変革期を迎えました。それまで、硝石、硫黄、木炭を主とした黒色火薬を原料とし、色は赤色の1色でした。それが、外国貿易の活性化に伴い、まずマッチの原料である塩素酸カリウムが輸入されるようになりました。次いで硝酸バリウム、アルミニウム、マグネシウムなどの薬剤が続々と輸入されました。これらの新薬を使い、赤、青、緑の発色に成功したのです。それまでの花火を和火、以降を洋火とよんでいます。いよいよ本格的な近代花火の時代に突入していきます。
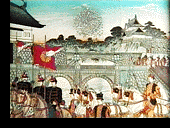
明治22年(1889)2月11日、大日本帝国憲法発布のとき、東京中がお祭騒ぎになりました。夜になると宮城の二重橋の中から花火が打ち上げられ、見物客はあまりの明るさと美しい色彩におおいに驚いたといわれます。
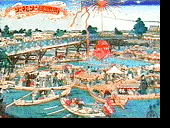
大正時代になると、割物(整然とした球状に開く花火)に工夫が加えられます。この時代に小割物と呼ばれる花火が考えだされました。小さな花が空にたくさん開くと、観衆からは拍手喝采が起きたと言われます。この時が花火の第2次革新期、花火師たちの制作意欲はどんどん高まっていきました。

大正から昭和にかけて、花火史上に名を残すような名人花火師が、全国各地で続出しました。
この時期の名人花火師達は、他の花火師には作りだせない強烈な印象を自らの花火に盛り込むように努力したのです。
昭和40年代、チタニウムが開発され、花火の第3次革新期を迎えます。これを花火に取り入れ『椰子』『千輪』といった新型花火が誕生しました。それまでは、割物花火のパッと咲いて、パッと散るのが、花火の醍醐味であったようで、当時、花火好きの一部からは「だらしがねぇ花火だ」ともいわれたそうです。時が移り、現在、日本の花火は世界に類をみないほどの精巧かつ豪華で、世界24ヵ国に輸出され、世界の夜空で美しい花を咲かせています。
スタ−マインは連続仕掛花火のことで、英和辞典にはない和製英語です。何十発何百発もの花火玉が短時間にテンポよく連続して打ち上げられます。咲いては消え、また華麗な花が咲き、ドンドドド−ンと腹を打つ轟音…その華麗で壮大な光景は、例えようもないものです。明治10年に天皇の長野行幸を祝し200発の花火が打ち上げられた「菊畑」が連発の最初です。

現代の花火はコンピュ−タ−制御。昔はわざわざ手で着火してたのを、コンピュ−タ−でより正確な計算のもと打ち上げられています。コンピュ−タ−の花火界進出により、以前よりたくさんの花火を連発で打ち上げることができるようになったのです。また近年、レ−ザ−光線との競演なども見ることができるようになりました。